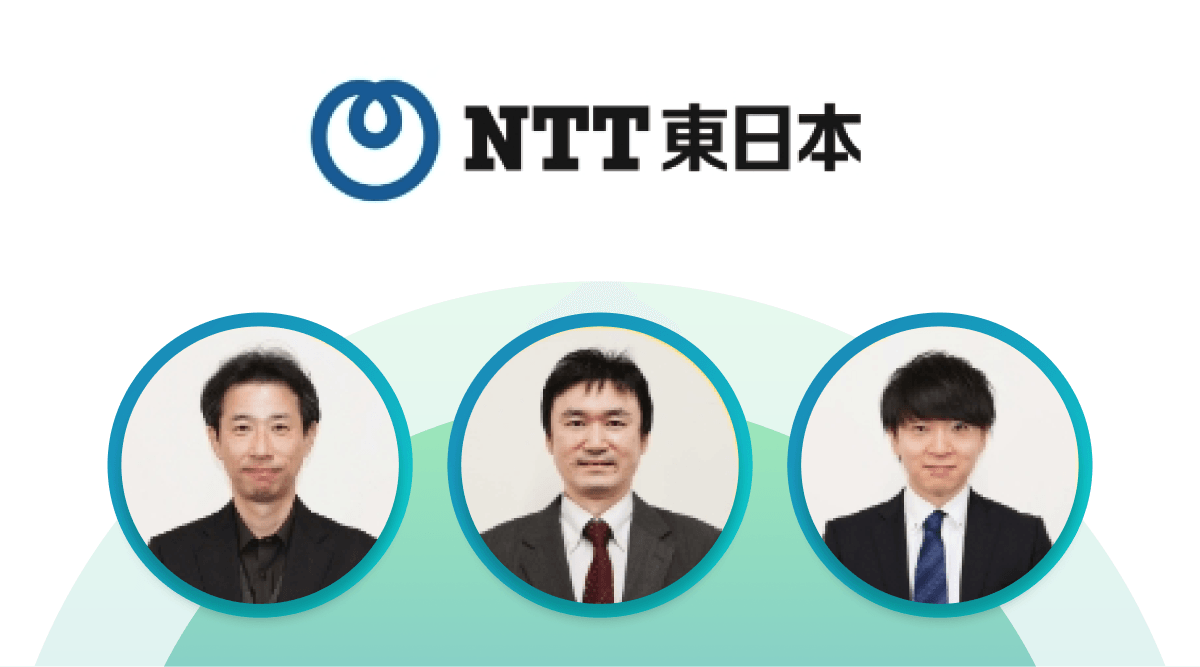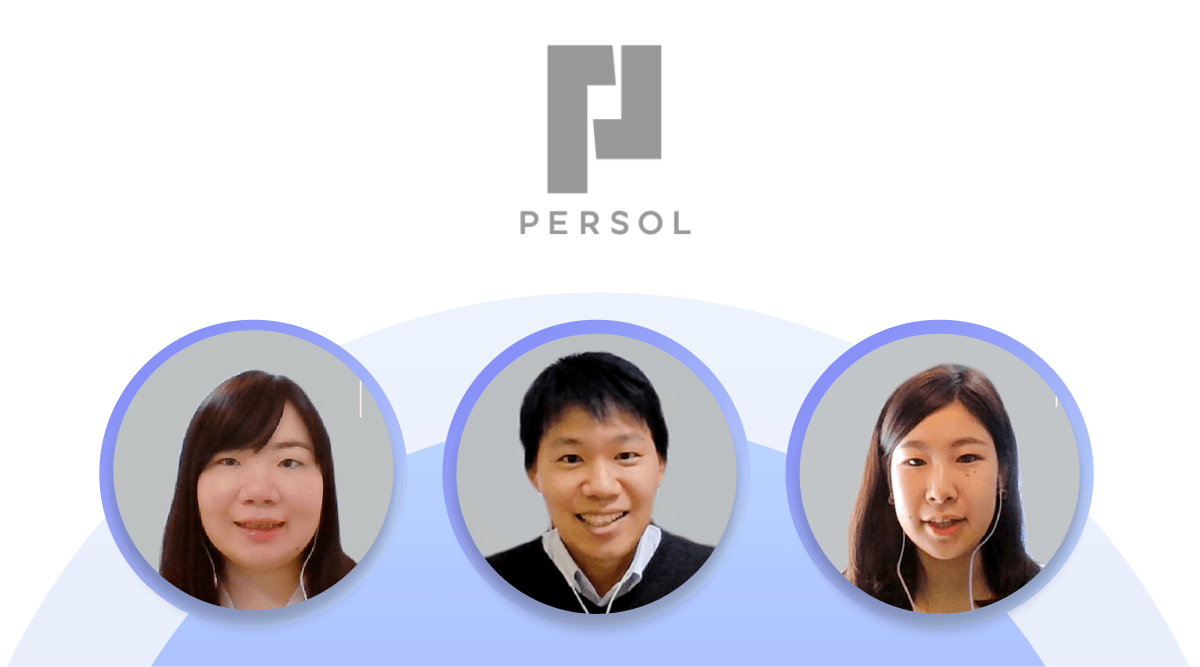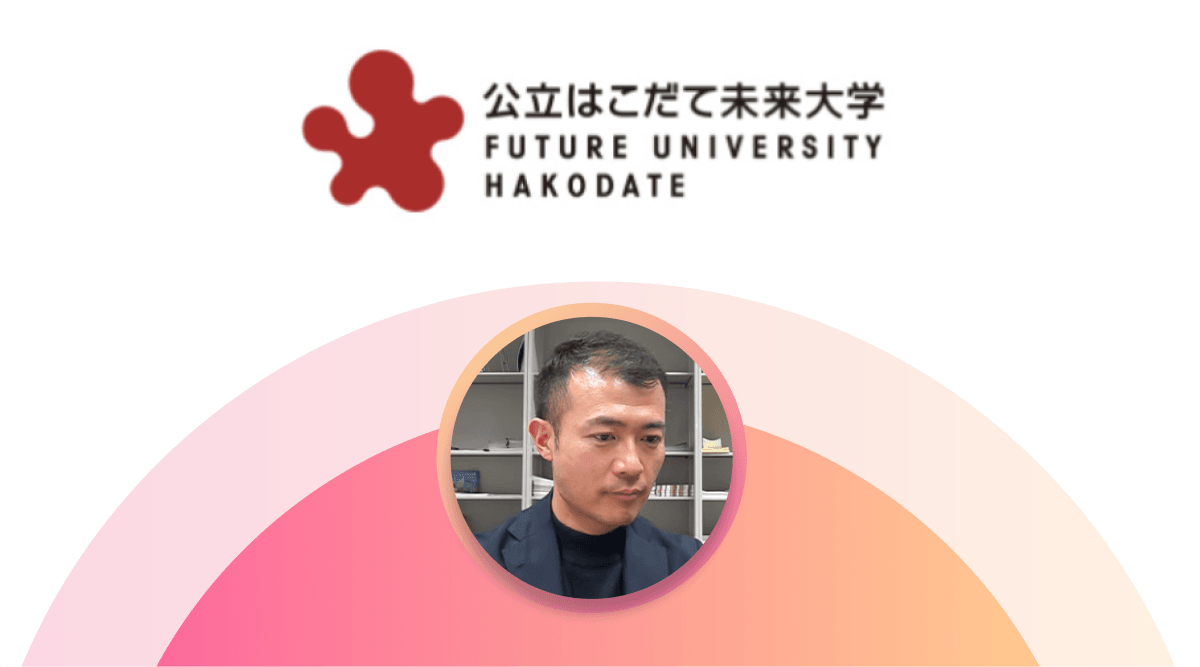インフォネットが取り入れた
会社への帰属意識を高めるツール
株式会社インフォネット
拠点間の情報連携の強化/コミュニケーションの活性化
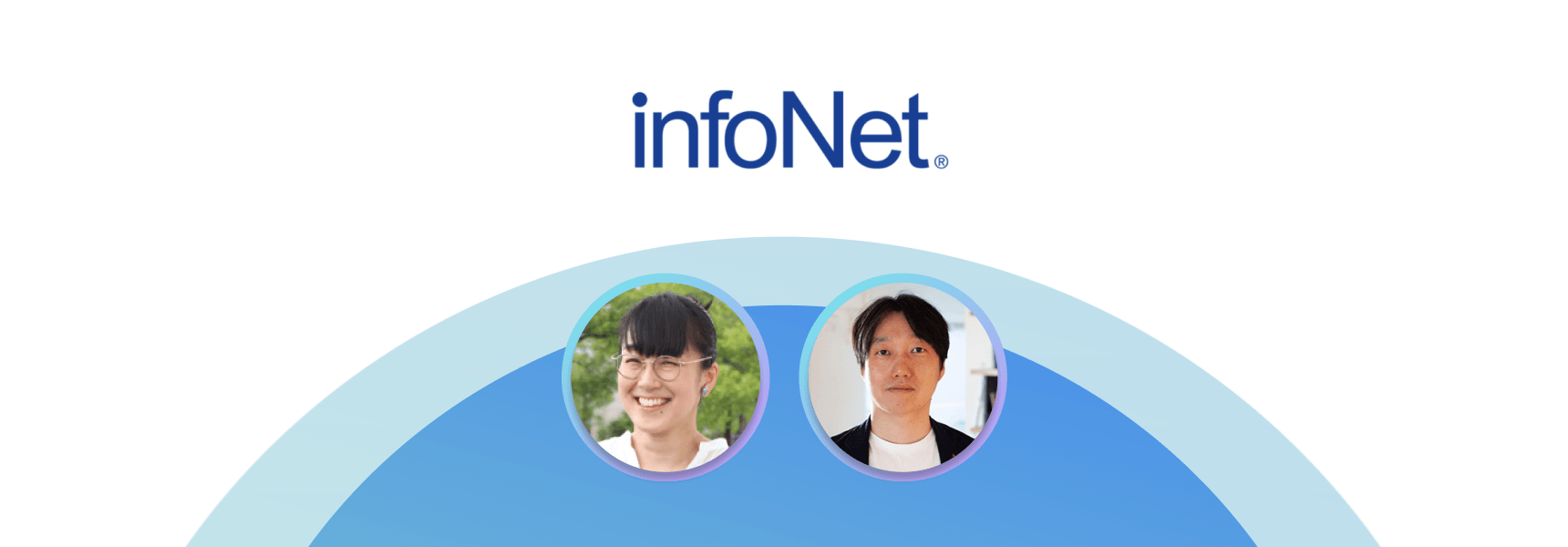
- 導入前の課題
-
- 拠点間で話すには会議を組む必要があって距離を感じる
- リモートワークになってコミュニケーションの量が減っている
- オンラインで大人数の雑談は声が被って話しにくい
- 選んだ理由
-
- 離れた拠点間でも気軽にコミュニケーションができる
- 相手の状態が見えて声がかけやすく、ちょっとした会話や相談に使える
- 検証のために少人数で運用したところ使い勝手がいいと好評
- 成果・効果
-
- 会議URLがいらないので、5分ほどの小さなミーティングがやりやすくなった
- 普段あまりコミュニケーションを取らない人にも話しかけやすくなった
- オンラインでも人がいる気配があって、一体感を得られるようになった
リモートワークで、コミュニケーションの「量」が減ったことにより、チームの一体感や会社への帰属意識が下がったという問題は、どの企業にとっても大きな悩みのタネです。
また、特にIT業界では、企業に属さずともフリーランスで仕事をする人も増えてきた中で、会社に所属することで得られるメリットやモチベーションを提供できなければ、社員の気持ちは離れていってしまいます。
SaaS型のCMS事業で大きなシェアを誇るインフォネットは、感染症拡大以前からリモートワーク導入のためのツールや制度の準備を進めていました。しかし、いざリモートワークがはじまると、急激にコミュニケーションの量が減り、一体感が下がっていることに悩みを感じていました。
そこで試しに使い始めたのが、NeWork。開発ディビジョンの50人に導入して、ちょっとした相談事や日々のコミュニケーションに使っています。NeWorkをチームに導入したProject Management & Development Division:管掌執行役員の藤本さん、実際にチーム内で毎日NeWorkを利用している同Design Unitの中村さんに、NeWorkによって、日々の仕事がどのように変化していったか、話を伺いました。

株式会社インフォネットについて
WEB/CMSサイト構築・AIプロダクト開発を行う総合IT企業。自社開発「infoCMS」を軸としたソリューションで、WEBマーケティングのトータルサポートサービスを提供している。
導入前の課題 コミュニケーションの「量」に課題
大手企業、官公庁自治体などを中心に、WEBデザイン・CMS・AIを活用した、サイト構築を行うインフォネット。2002年に福井で創業し、東京へ。そこから規模を拡大し、現在は東京と福井のほか、佐賀、大阪にも拠点を持っています。
拠点間のコミュニケーションは、内線電話やチャットツール。また複数人の会議もスムーズにするため、オフィスの会議室に大きなモニターを設けテレビ会議をしやすくしていました。
ただ、福井オフィスで開発チームに所属する中村さんは、どうしても拠点と拠点の間に一体感がないと感じていたといいます。
「拠点間のコミュニケーションは、リモートワークになる以前から課題を感じていました。1対1であればちょっとした相談ごとは内線電話で済んでいたのですが、拠点をまたいで数人でちょっと集まって話したいとなると、わざわざ会議を組まなければならない。ここにストレスを感じていました。年一回の全社会議でしか顔を合わせる機会がなかったので、拠点間の距離を感じる節はありましたね」(中村さん)
さらに、新型コロナウイルス感染拡大で、拠点関わらずほとんどの社員がリモートワークへ移行。もともとリモートワークの導入を進めていたこともあり、デバイスやコミュニケーションツールなど、ハード面の移行はスムーズに進みました。
しかし、課題が。それがコミュニケーションの「量」でした。

株式会社 infoNet
Design Unit
中村彩氏
「もともとオンラインでのやりとりは慣れていたのでコミュニケーションの質には問題がなかったのですが、量はどうしても少なくなったと感じていました。絶対量が少ないとちょっとした会話や相談もしづらくなります。日を追うごとに、ケアの必要性を感じていましたね」(藤本さん)

株式会社 infoNet
Project Management & Development Division
管掌役執行役員
藤本太一氏
大人数だとオンラインで雑談をするのも一苦労
経営層の中でも「会話や雑談が足りない」ということは課題に。そこで、社内ルールとして毎日雑談時間のルーティンを設けることになりました。
その名も「ザッソウタイム」。毎日30分決められた時間にごとにzoomをつないで雑談をしよう、という仕組みでした。
会社の仕組みとして、「雑談」の時間をきちんと設けるというのは素晴らしいことなのですが、実はこの仕組み、中村さんのいる20人ほどのチームにとっては、なかなか大変だったといいます。
「私がいた部署が10〜20人ほどの大きめのチームだったため、自由に雑談してしまうと声がかぶってしまったり、発言しづらい人が出てきてしまったり、運営が難しいなと感じていました。毎日交代で司会を回したり、お題を考えたりもしたのですが、もう少しいいやり方はないかなと悩んでいました」(中村さん)
中村さんは、この事態を藤本さんに相談。そのとき、ちょうど藤本さんが検証していたのがNeWorkでした。
「どんなサービスなんですか?と、藤本さんにNeWorkのサービス画面のキャプチャを見せてもらったんです。それを見た瞬間に、『これだ!これが求めていたサービスです!』と興奮して、ぜひチームで使いたいとリクエストしました」(中村さん)
藤本さんはまず、検証のために10名ほどのチームでまず小さく運用を始めましたが、使い勝手がいいと好評に。そこでガイドラインを作って、50人に導入しました。
成果・効果 人の気配を感じ、帰属意識が高まるUI UX

そこから、8ヶ月。中村さんのチームでは、常にNeWorkをたちあげてコミュニケーションを取っています。
執務室と会議室、集中ルームの3つに分け、相談があるときには会議室へ。集中ルームは窓際の個人ブースのようなイメージです。
「URLを作らないので、誘う方も誘われる方も小さい労力で、5分10分の小さなmtgがやりやすくなりました。相手の状態も見えるので、声もかけやすいですし、他の人も誰と誰が話しているか分かるので閉鎖的にりません。普段あまりコミュニケーションを取らない人へも話しかけやすくなりました」
リモートワークの広がりやそれに伴う各種ツールの進化により、WEB制作・開発業界でも、スピード感とクオリティの共存がより求められるようになったと藤本さんは実感しています。そういった面からも、会社の経営視点でもコミュニケーションの密度の重要性は高まっています。
「コミュニケーションを円滑にする仕組みがあるかないかで、仕事のスピードや成果物が大きく変わってきます」
おふたりが気に入っているポイントは?と尋ねたところ、「音」だと教えてくれました。人が出入りするときに鳴る「ピロン」という効果音。作業しているときに肩を叩くように「〜〜さん」と、かけられる声。
「家でずっと作業をしていると、オンラインミーティングが終わった瞬間、しんとした部屋に”ひとり”取り残される、あの孤独感が寂しかったんですよね。NeWorkだと、会議室で話した後、執務室に戻る感じ。人がいる気配を感じられて、ああ、この会社で働いているんだなっていうことを感じられるんです」
どこにいても一体感や安心感を得られる環境を
オンラインコミュニケーションがシームレスになることで、拠点や場所にとらわれることがなくなっていくと、中村さんは話します。
「これまでだと、どうしても福井にいて損していると感じることがありました。これからは、仕事と場所が関係ないような働き方になっていくのかなと思っています。NeWorkのおかげで、リモートワークになってなくなりそうになっていた会社の存在をほんわか感じています。これからも使い続けて、会社としての一体感をもっと感じられるようになるといいなと思います」(中村さん)
今の時代、IT業界では個人でフリーランスという働き方もスタンダードになりつつあります。その流れの中で、会社に所属して働く意味を作らなければ、と藤本さんは感じています。
「困ったときに聞ける人がいる安心感や、自分だけではできない成長ができるという、会社に所属するメリットを感じられる環境づくりをしていかないといけないなと、感じています。どこでも働けて、どこにいても一体感や安心感を得られる環境をどう作り出すか、可能な限り追求していきたいと思っています」(藤本さん)